Last Updated on 2025年2月18日 by tommy1106
記事内に商品プロモーションを含む場合があります
作曲に夢中になっているのに、思うような曲が作れずに悩んでいませんか?
音楽理論の壁にぶつかり、アイデアを形にできないフラストレーションを感じていませんか?
作曲を勉強するのに本を利用することはコスパが良く、
あなたの音楽の世界を広げる鍵となるでしょう。
私も以前は同じ悩みを抱えていました。
メロディは浮かぶのに、それを魅力的な曲に仕上げる技術が不足していたのです。
しかし、適切な本に出会い、作曲の基礎から応用まで体系的に学ぶことで、
自信を持って曲作りができるようになりました。
作曲の学習には、信頼できるガイドが不可欠です。
- プロの作曲家のテクニックや考え方を学べる本
- 音楽理論や楽器の知識を深められる本
- DTMソフトの使い方や音楽制作の実践的なノウハウが載っている本
これらが、あなたの創造性を解き放つ力となるのです。
しかし、世にはたくさんの本が出版されており、どれから読めば良いのか
判断がつかないですよね?
今回は、幅広いレベルに対応した作曲を勉強するのに役立つ本をご紹介します。
これらの本は、あなたの音楽スキルを確実に向上させ、
より魅力的な曲作りへと導いてくれるでしょう。
音楽の世界には無限の可能性があります。
今すぐ行動を起こし、あなたの才能を開花させましょう。
この記事を読み進めれば、あなたに最適な作曲の勉強がスムーズになる本が見つかるはずです。
さあ、新たな音楽の扉を開く準備はできましたか?
この記事では作曲、DTMを始めたばかりの方にこの順番で読めば
正しく上達出来る、オススメの本を3冊紹介したいと思います。
作曲、DTMを勉強するための本を選ぶ基準
ここでは、作曲やDTMを勉強するために本を選ぶ基準を解説しますので、
ご参考にされてください。
自分のレベルに合った本を選ぶ
世の中にはそもそも『読書大好き』、『本なんか全く読まない』色々な方が
いらっしゃると思います。
作曲、DTMを学ぶにあたっては、現在どれくらいの知識をお持ちかにも寄りますが、
音楽理論やコード理論自体が深く学ぶと非常に難しいので、
読書好きの方でも少し壁を感じてしまうのではないでしょうか?
全く音楽理論なんて知らないよって方が分厚くて、文字がギッシリの本は
かなりハードルが高いです。
特に作曲やDTMを始めたばかりの方には、基礎から丁寧に解説している本がおすすめです。
- 音楽理論の基礎:コードやリズム、スケールなどの基本概念を学べる本
- 作曲の入門書:メロディの作り方やコード進行の基礎を解説した本
- DTMソフトの使い方:人気のDAWソフトの操作方法を解説した本
最初に選ぶ選択肢はこんな感じだと思いますが、
自分が今何を学びたいのか?自問自答するのもいいかもしれませんね。
今の自分が少し難しい程度と感じるレベルのものを教材にするのもオススメです。
実践的な内容を重視する
私が本で作曲やDTMを学びたいと思った時に重視するのは以下の2点です。
- 図解などが多めで簡単そうか?
- 手を動かしながら読み進められるような形式か?
理論だけでなく、実際に曲を作る過程をステップ・バイ・ステップで
解説している本が望ましいです。
作曲エクササイズみたいな感じの、実践的な内容を含む本を選ぶことで、
学んだことをすぐに応用できます。
補足資料の有無を確認
私はこれまで作曲やDTMを勉強するために数十冊以上の本を読みましたが、
たいがいの本には付録がついており、ネット上で音源を確認出来たり、
オーディオファイルやMIDIファイルをダウンロードして
自分のDAWソフトに取り込めるものが多かったです。
これは、結構重要に思っていて、ただ本を読むだけでなく
実際に手を動かしたりしながら、自分のオリジナル曲でないにしても
一つの形になっていくのは、とても楽しいですし、
まさに学びながら、形になっていくので、モチベーションアップにも
つながります。
では、作曲やDTMを勉強するのにオススメの本を紹介していきますね!!!
作りながら覚える3日で作曲入門/monaca:factoryさん
これは本当に素晴らしい本です。
特にまだ1曲も完成させたことがないという方には超超オススメしたい本です。
著者のmonaca:factoryさんが、従来の音楽理論から始める方法とは
異なるアプローチで作曲を学べるよう工夫されてますね。
本書では、理論を後回しにし、まず1曲を作ることから始めます。
3日間で1曲を完成させる手順が丁寧に説明されており、
初心者でも挫折せずに最初の1曲を作り上げることができます。
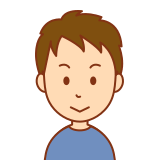
今日初めてDAWを触るって方でも、出来るほど
分かりやすく説明されているよ!
まだDAWソフトをお持ちでない方も考慮されていて、
Windowsユーザーさんには『Domino』、Macユーザーさんには『GarageBand』という
無料で使えるソフトも紹介されています。
私も最初の頃は、Dominoを使ってました、あ~懐かしい・・・。
もちろん、すでにDAWソフトをお持ちの方はご自分のDAWソフトを
お使いの上、進めていただけます。
3日で1曲作るというコンセプトで1日目はこれ、2日目はこれという感じで
順序立てて説明されています。
こういうの個人的にわかりやすくて大好きです。
専門用語的な表現も少なめで、何もわからないといった人も
迷わずサクッと進めていけるのではと思います。
手を動かしながら進めていくことで、楽しみながら記憶にも定着させることができますね。
前半部分で1曲を完成させて、後半部分では曲をかっこよくするテクニックを
わかりやすく解説されています。
全体的に文字数ギッシリではなく、何か友達が教えてくれているような
感覚であっという間に最後まで読み切ることが出来ました。
作曲を始めたい、やりたいけど全然わからないといった方には
一番オススメの本です。
スグに使える コード進行レシピ/斉藤 修さん
こちらは何曲か作ってはみたけど、イマイチかっこいいコード進行が出来ない、
もう少しで初心者の域を出れるかなぁといった方にとてもオススメの本です。
世にコード進行について解説されている本はたくさんあります。
ただすごく難しいものも多くて、途中で読むのが嫌になる本もたくさんあります。
その本が悪いのではなく、自分がその本を読むレベルにまだないというのもあると思います。
また、複雑なテンションコードをたくさん紹介している本も自分はあまり好きではないですね。
ジャズ的な雰囲気は個人的にあまり好きではないのと、ロック、ポップス系の曲を作るのに
使い所が難しいし、そこまで必要がないのではと感じてしまいます。
その点、こちらの本では少しはそういったことも出てきますが、
大半はそんなに複雑なコードは使わずに、でもカッコいいみたいなパターンが満載です。
最初にコード理論の解説がありますが、すごくわかりやすくまとめられていて
少しでもコード理論を学んだ方であれば、スルッと読んでいけるのではと思いますし、
コード理論を学んでいない方でも、ギュッと凝縮されて必要な理論が
まとまっているので、トライしてみるのもアリだと思います。
そして理論の解説が終わると、カッコいいコードパターンがこれでもかと
たくさん紹介されています。
私もたくさん学ばせていただきましたし、今でも読み返したりさせていただいてます。
コード進行は、Los Angeles、New York、Londonなど、
様々な都市のテイストをテーマにした章に分けられていているのもいいですね!
オススメの使い方は
- 出ているコード進行をそのまま打ち込んで聞いてみる
- 本に記載のリットー・ミュージックさんのダウンロードサイトから
MIDI DATAをダウンロードして、DAWソフトにデータを取り込み、実際に聞いてみる - 自分で合いそうなコードに入れ替えてみる
実際に手を動かして、DAWソフトに読み込んで聞いてみたり、
自分なりに今持っている知識でコードを入れ替えてみると
『はっ、今のカッコいい』というパターンに出会うはずです。
パターンごとに解説もありますので、『あ~、こういうコードを使うとカッコいいのかぁ』と
納得感を持ち、これを自分の曲に使えないかなぁと考えることで
自分の作曲の引き出しを増やすことが出来ます。
自分の作るコード進行ってありきたりだなぁと感じてる方には
ぜひ読んでいただきたい1冊です。
Amazonの電子書籍、Kindle Unlimitedを利用すれば月額980円で対象書籍が読み放題です。
こちらの書籍は現在は読み放題対象なので、1冊読めば、元が取れてしまいますね。
無料体験期間があったり、月額料金が割引になっている場合もありますので、
まだ、Kindle Unlimitedを利用されていない方は、
下記のリンクから、ぜひ、確認してみて下さい。
ポピュラー音楽作曲のための旋律法 増補版/高山 博さん
作曲の悩みにメロディーが作れないということは多いと思います。
こちらの本はこれでもかというくらいメロディーに特化した本で
他に似たような本は見当たらないと思います。
この本を読んだからすぐにメロディーが作りやすくなるということでは
ないかもしれませんが、いろいろな視点からメロディーについて
解説をされているので、新たな発見があるのはまちがいありません。
音の運動と旋律の体験から始まり、
音高、音程、音長、音価、拍子、リズム、旋法、和声、歌詞、楽曲構成に至るまで、
メロディ作りに関する幅広いトピックをカバーしており、
各章では、それぞれの要素が聴き手にもたらす効果を詳細に解説しています。
音符の上行下行や長短、コードとの関係、リズムの符割など、
メロディラインの動きが聴き手に与える影響を実例を用いて紹介しています。
これにより、理論を実践に結びつけやすくなっており、
聴き手の心に響くメロディラインを作るための具体的なヒントを提供しています。
Amazonの電子書籍、Kindle Unlimitedを利用すれば月額980円で対象書籍が読み放題です。
こちらの書籍は現在は読み放題対象なので、1冊読めば、元が取れてしまいますね。
無料体験期間があったり、月額料金が割引になっている場合もありますので、
まだ、Kindle Unlimitedを利用されていない方は、
下記のリンクから、ぜひ、確認してみて下さい。
AmazonのKindle Unlimitedを利用してみる
私は以前にAmazonのKindle Unlimitedを利用しておりましたが、
自分の読みたい本が対象になっていない(無料で読めない)ことがあることが多くて
止めておりました。
最近になって、音楽系で読みたい本が10冊位出てきたので、
久しぶりに調べてみると、10冊中9冊が無料で読めることが分かり
また、利用してみることにしました。
ちなみに私は年会費を払ってAmazonのプライム会員になっておりますが、
プライム会員でなくても、Amazonの会員でさえあれば、
Kindle Unlimitedは利用出来るそうです。
月額利用料は980円ですが、機会によっては
初月無料キャンペーンとか月額利用料割引のキャンペーンが
実施されることもあります。
AmazonのKindle Unlimitedを利用するメリット
- 初月無料で利用出来る(2023年1月の時点)
- 月額980円の利用料を払っても、月1,2冊読めば元が取れる
- パソコンでDAWソフトをいじりながら、スマホで確認出来る。
- 自分の利用履歴からオススメの本を紹介してくれるので、
知らない本の存在がわかったり、次に読みたい本を探しやすくなる。
AmazonのKindle Unlimitedを利用するデメリット
- すべての本が無料というわけではない
- 対象が変わることがあるので、それまで読んでいた本が読めなくなることがある。
- 特に音楽系の本はスマホで読む場合、字が小さくて読みづらい。
とはいえ、メリットの方があまりにも大きく
読書大好きな自分にとっては信じられないサービスです。
毎月、音楽系の書籍1冊、通勤時にお好みの書籍を1冊
読書ライフを始めてみるのはいかがでしょうか?
おまけ編:オススメの3冊を読んだ後にもっとレベルアップしたい方へ!
上記3冊を読んだ後にオススメしたい本を記事にしてみました。
なぜ、この記事で紹介しなかったかというと、何も音楽理論やコードの知識が
ない状態で読むと非常に難しいと思うからです。
でも、ある程度学んだ後で読むと非常に学べることが多いので、
興味のある方は、ぜひこちらの記事も覗いてみて下さい。
まとめ:作曲の秘訣を掴む!勉強のポイントとオススメ本3選でレベルアップ
残念ながら、2025年2月18日現在
『作りながら覚える3日で作曲入門』はAmazonのKindle Unlimited対象外のようです。
しかし、本当に良い本ですし、お金を出して購入しても後悔はないと思います。
私もAmazonのKindle Unlimitedをフル活用してこれからも
どんどん大好きな作曲、DTMの知識を増やしていきたいと思っております。
今回ご紹介した3冊をお読みいただければ、
作曲の基礎知識→コード進行→メロディが体系的にわかり
みなさんの音楽制作が一段レベルアップ出来るのではないかと思います。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
皆様の作曲、DTMのスキルアップに何か貢献できていれば
とても嬉しいです。





コメント